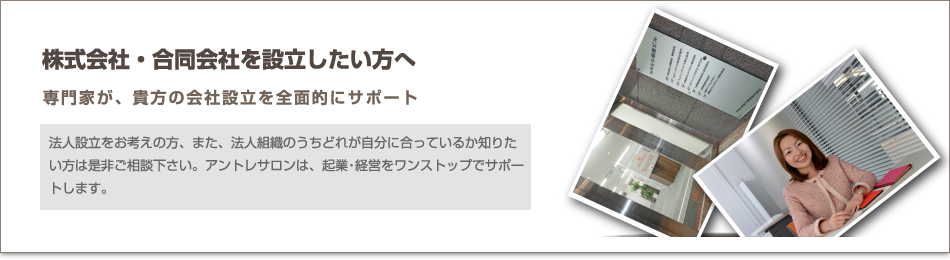
法人化する場合、どの組織形態にするかを決めます。
法人には大きく分けて、営利法人(株式会社、合同会社など)と、非営利法人(一般社団法人、一般財団法人、NPO法人など)があります。
「営利」は、組織として上げた利益を構成員(株主など)で分配し、「非営利」は、利益を構成員に分配せずに組織を運営します。営利の中でも一般的に普及している組織形態は株式会社です。また、合同会社(LLC)も増えています。これは2006年の会社法施行に伴って新設された会社形態です。
株式会社と合同会社の大きな違いは設立費用です。株式会社は約20万円、合同会社は6万円で法人設立が出来ます。また、株式会社は社会的な認知度が高いですが、増えているとはいえ合同会社の場合、株式会社程の認知度はありません。組織形態を選ぶ際は、事業の内容や、ターゲット顧客、事業展開の計画などを念頭に入れ、検討しましょう。なお、どちらの組織形態も一人で設立ができます。
法人設立は、株式会社の場合、次のような流れになります。
(イ)定款作成
(ウ)公証役場において定款の認証
(エ)資本金の払込
(オ)法務局への設立登記申請
(カ)登記の完了
なお、弊社のお客様にもよく聞かれるのですが、法人の設立日は、上記の(オ)の法務局へ設立登記申請を行った日となります。また、合同会社の場合、(ウ)に書かれている公証役場での定款の認証がありません。書類を作成したら、法務局への設立登記の申請のみで設立が可能です。
上記に挙げた法人設立の手続きの中でも、(イ)の定款の作成方法が分からないという方が多いので、説明します。
定款とは、会社の基本ルールを定めたものです。作成するために以下の項目を決める必要があります。それぞれの項目について触れておきます。
・商号(会社名)
・事業目的
・本店所在地(住所)
・資本金
・事業年度
・役員
株式会社の場合、商号には会社名の前後に「株式会社」という文字を含めなければなりません。旧商法では類似商号の規制に注意が必要でしたが、現在の会社法では、本店住所が同一でなければ、原則として類似の商号も認められます。ただし、特定の業法で規制されている業種の名称(例:○○銀行)、「支店」や「事業部」など会社の一部門を表すような名称は、商号として用いることができません。設立の申請にも使用する為、商号が決まったら、会社の実印(代表者印)を作成します。
事業目的は、会社がどのような事業を行うことができるかを定めるものです。目的は複数記載できるので、起業時の事業だけでなく、将来的に行う可能性のある事業も含めておきましょう。許認可が必要な事業(例:人材派遣業、飲食業など)を行う場合は、許認可申請時にその事業目的を入れておかなければなりません。後で許認可を取得しようと思ったときに、事業目的の変更が必要になると、登記変更の為の費用がかかってしまうので、目的を決める時点で確認しておきましょう。
本店所在地(住所)について、自宅や賃貸オフィスなどの住所を登記する場合は、賃貸契約や管理規約などで事業目的が制限されていないかどうか、念のため確認しましょう。賃貸オフィスだけでなく、レンタルオフィスを登記住所とすることも可能です。業種によっては場所のイメージも重要です。本店所在地は慎重に検討しましょう。
資本金は、以前の商法では最低資本金制度(1,000万円)がありましたが、現在の会社法では規制はなく、1円でも設立が可能です。とはいえ、実際にはオフィスや什器備品などの初期投資や、当面の運転資金が必要ですので、資金計画に基づいて、ある程度の余裕を持っておきましょう。また、創業融資などを受ける予定がある場合は、自己資金額が審査要件となりますので、そのバランスも考慮して適正な資本金額を検討する必要があります。
なお、設立登記申請時は、資本金の払込を証明する書類が必要です。会社設立の発起人(複数いる場合は代表者1名)名義の銀行口座に振り込み、その通帳のコピーを会社代表者名で作成する払込証明書とともに、法務局へ提出することになっています。
資本金は、金銭での出資に限定されているわけではありません。パソコンや有価証券、自動車などの財産で出資することも可能で、これを「現物出資」といいます。原則としては、出資した財産の価額が適正かどうかを評価するために、裁判所が選任する検査役の調査が求められますが、現物出資の総額が500万円以下であれば、調査は不要です。手持ちの現金に余裕があまりない場合は、現物出資の活用も検討しましょう。
一般的には設立した月から事業年度が始まり、翌年の設立月の前月末までというのが多いです。例えば6月10日に設立した場合、事業年度は6月1日から翌年の5月末までとなります。この場合、決算期は5月になります。
役員は、取締役1名がいれば設立できます。株主も自分1人、役員も自分1人という1人起業の方が多いです。
会社の設立登記に必要となる申請書類にはさまざまなものがありますが、中心になるのは「定款」です。先にお話しした項目のほか、決算など重要事項の公告方法や株式の譲渡制限事項、取締役の定員数などを決めて定款を作成します。作成した定款は公証人役場の認証を受け、その他の登記申請書類をそろえたうえで、法務局で登記を行うことになります。
なお定款は、紙ではなく、PDFファイルによる電子定款で認証を受けることによって、収入印紙4万円分を削減できるという費用的なメリットがあります。登記が完了したら、税務署などへの法人設立届や銀行口座の開設など、諸手続きが必要になるので、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)や印鑑証明書を取得しましょう。

調査期間:2023年1月13日~2023年1月16日
調査元:JAPAN TRUST RESEARCH
対象:20代~60代の女性・男性(n=105)
インターネット・アンケート調査