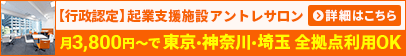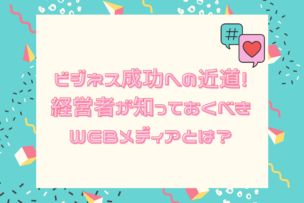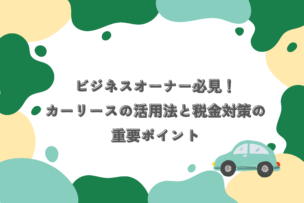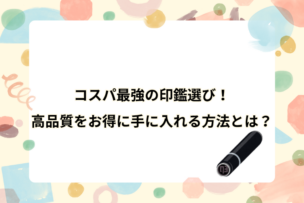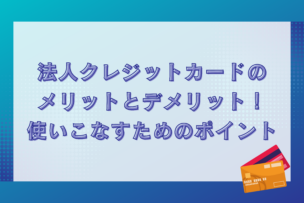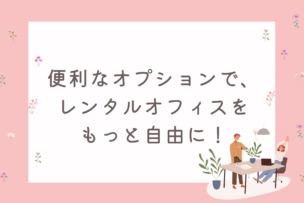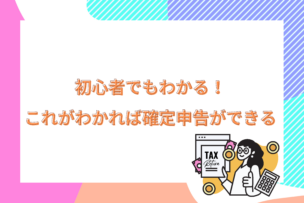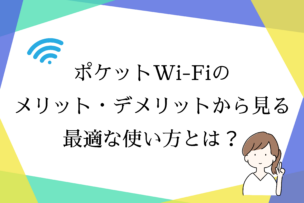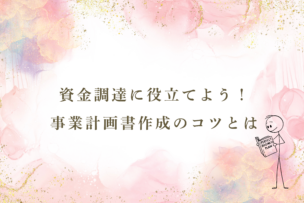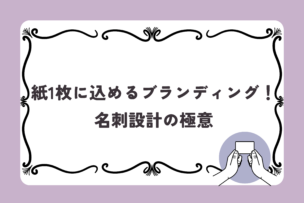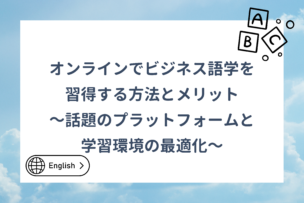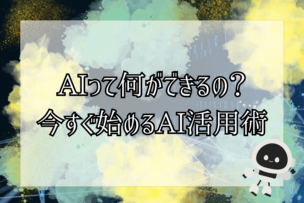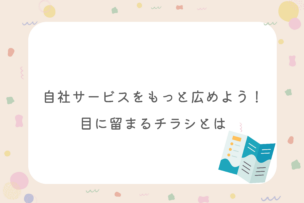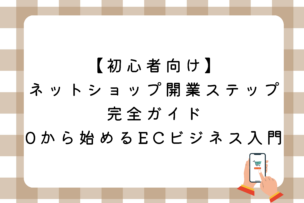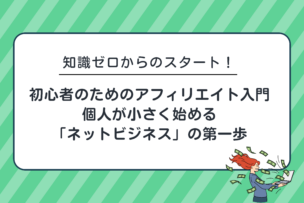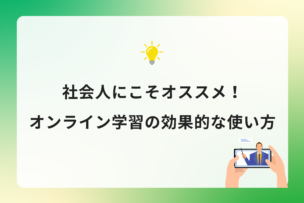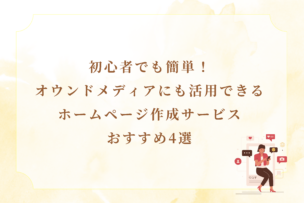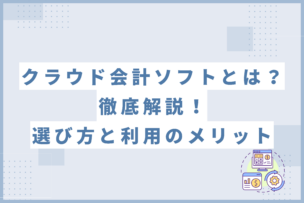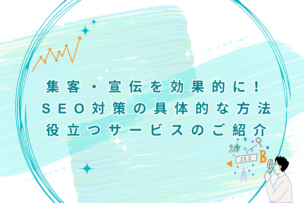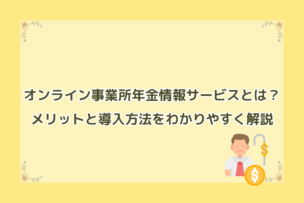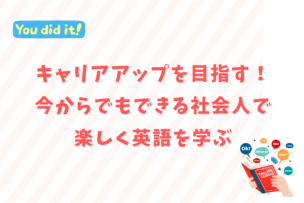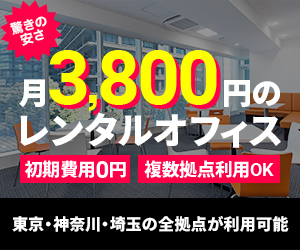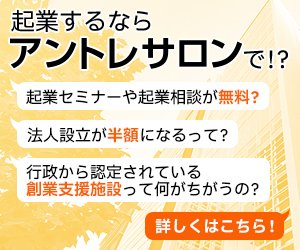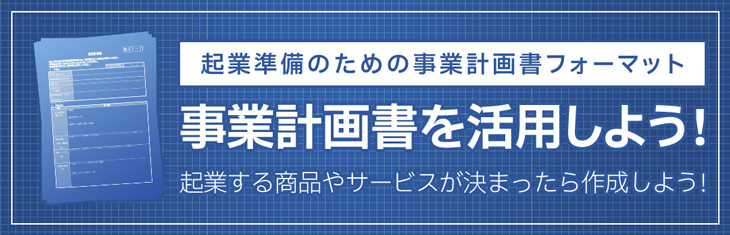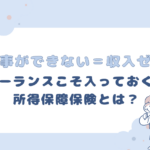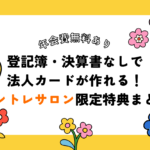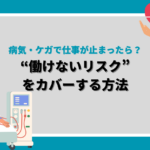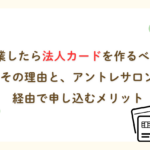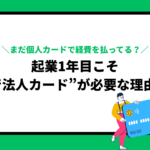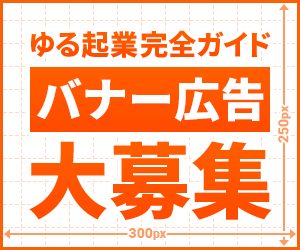経営者としての成功には、継続的な情報収集と柔軟な対応力が欠かせません。業界の最新情報や他社の成功事例を学ぶことは、ビジネスを成長させるための重要な要素です。しかし、すべての情報を把握し、活用するのは非常に大変です。そんなときに役立つのが、WEBメディアです。 WEBメディアを活用することで、忙しい経営者でも効率的に情報収集ができ、成長に繋がる知識を得ることができます。この記事では、経営者が知っておくべきWEBメディアをいくつか紹介し、それぞれの特徴や活用法について解説します。これらのメディアを上手に活用すれば、ビジネスの成長を加速させ、スキルアップに繋げることができるでしょう。
お役立ち情報の記事一覧
ビジネスオーナー必見!カーリースの活用法と税金対策の重要ポイント
ビジネスオーナーにとって、車は必要不可欠なアイテムであり、業務の効率を左右する大事な設備です。特に営業職や配送業務を行っている場合、車両の保有や維持は重要なコスト項目となります。しかし、車の購入やリースには、いくつかの選択肢があり、それぞれに税金面でのメリットやデメリットが存在します。今回は、ビジネスオーナーとしての視点から、カーリースの活用法と税金対策の重要ポイントを紹介します。
コスパ最強の印鑑選び!高品質をお得に手に入れる方法とは?
ビジネスでもプライベートでも、印鑑は日本の生活に欠かせないアイテムです。就職、転職、結婚、開業など、人生の節目には必ずと言っていいほど印鑑が登場します。 でも、いざ「印鑑を買おう」と思ったとき、こんな疑問を持ったことはありませんか?
印鑑ってどれを選べばいいの? 安くてもちゃんと使えるの? 高い印鑑と安い印鑑の違いって何?
この記事では、「コスパ最強」の印鑑を見つけるためのポイントと、高品質な印鑑をお得に手に入れる方法をご紹介します。さらに、おすすめの信頼できる購入サイトも最後にご案内します!
法人クレジットカードのメリットとデメリット!使いこなすためのポイント
法人クレジットカード(法人カード)は、企業活動の中で欠かせない経費管理のツールです。経費精算の効率化やキャッシュフロー改善に貢献する一方、誤った運用によってはリスクを招くこともあります。
起業後に、法人用のどのクレジットカードにしようか迷っている方も多いです。本記事では、法人カードのメリットとデメリットを整理し、企業として賢く使いこなすためのポイントをご紹介します。
便利なオプションで、レンタルオフィスをもっと自由に!
アントレサロンは、東京・神奈川・埼玉を中心に展開するレンタルオフィスです。お客様が必要なサービスを必要な分だけ組み合わせて利用ができるように多様なオプションサービスをご用意しています。今回は、そんなアントレサロンのオプションサービスについてご紹介します。
初心者でもわかる!これがわかれば確定申告ができる
確定申告は、税金に関する重要な手続きですが、初めての方にとっては難しく感じることも多いですよね。この記事では、確定申告の基本的な流れを、初心者の方にもわかりやすく解説します。これから確定申告をしなければならない方、またはこれから始めたいと思っている方も、安心して読んでくださいね!
ポケットWi-Fiのメリット・デメリットから見る最適な使い方とは?
テレワークや外出先での仕事、引っ越し直後のネット環境確保など、ポケットWi-Fiの需要が高まっています。ですが、「ポケットWi-Fiって速さや容量が心配」「どれを選べばいいの?」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
今回は、ポケットWi-Fiのメリット・デメリットと最適な選び方をお伝えします。最後には、オススメのポケットWi-Fi4選を比較表でご紹介します!
資金調達に役立てよう!事業計画書作成のコツとは
起業を目指すあなたにとって、事業計画書は単なるアイデアの整理ではなく、ビジネスの未来を形にするための「戦略ツール」です。明確な計画があることで、資金調達の成功率が高まり、事業の信頼性や成長可能性も飛躍的に向上します。本記事では、事業計画書が果たす重要な役割や、作成を効率化するツールの活用法、さらにビジネススキルを磨くための学びの場まで、起業を成功に導くための実践的なヒントをご紹介します。
紙1枚に込めるブランディング!名刺設計の極意
― 自分を伝える、たった一枚の設計図 ―
名刺は、初対面の相手に自分を印象づけるための、最初のツールです。デジタル化が進んだ現代においても、名刺は“手渡し”という行為を通じて、信頼や存在感を伝える重要なコミュニケーションツールであり続けています。 SNSやメールでは伝わりにくい、質感やデザインの「印象の強さ」。名刺一枚に、その人の仕事への姿勢や美意識、ブランドコンセプトまでも感じ取ることができるのです。 だからこそ、名刺づくりは“単なる印刷”ではなく、“自己表現”であると言っても過言ではありません。 本記事では、名刺の役割や設計のポイントに触れながら、高品質で信頼できる名刺作成サービスを3つご紹介します。
オンラインでビジネス語学を習得する方法とメリット ~話題のプラットフォームと学習環境の最適化~
グローバル化が加速する現代、ビジネスシーンでの語学力はますます重要になっています。英語はもちろん、中国語やスペイン語、ドイツ語といった多言語スキルは、海外との交渉・メール・プレゼンにおいて差を生み、キャリアアップにも直結します。とはいえ、忙しいビジネスパーソンにとって、時間や場所に縛られた語学学校に通うのは現実的でないことも多いでしょう。そこで注目したいのが、オンラインでのビジネス語学習得です。
AIって何ができるの?今すぐ始めるAI活用術
― あなたの仕事を劇的に変えるAIの力とは ―
近年、AI(人工知能)という言葉をよく耳にするようになりました。多くの人々が「AIは難しそう」「使いこなせる自信がない」と感じているかもしれませんが、実際にはAIは非常に身近で、誰でも簡単に活用できるツールが揃っています。今回は、AIを活用することで、どんなことができるのか、どこから始めればよいのかを解説し、実際にすぐに使える3つのAIツールもご紹介します。これを読めば、AIの使い方がもっと身近に感じられるはずです。
自社サービスをもっと広めよう!目に留まるチラシとは
チラシは、宣伝活動の中でも手軽で効果的な手段のひとつです。しかし、ただ配布するだけでは十分な効果を得ることは難しいです。目に留まる、そして印象に残るチラシを作成し、適切な場所に掲出することで、自社サービスを広めることができます。 また、チラシはアナログな手法ですが、起業初期に「認知を広げる」「反応を見る」「信頼を作る」ためのリアルで強力なツールでもあります。逆にデジタル広告のリーチが届きづらい層には、チラシが最もコストパフォーマンスの高い手段となる場合があります。今回は、チラシ掲出サービスや、チラシ作成サービスを活用して、効果的な宣伝方法をご紹介します。
【初心者向け】ネットショップ開業ステップ完全ガイド|0から始めるECビジネス入門
ネットショップを始めてみたいけど「何から始めればいいかわからない」……そんな方のために、この記事では完全初心者でも分かるネットショップ開業のステップを、順番にわかりやすく解説していきます。
副業で始めたい方、ハンドメイド作品を売ってみたい方、実店舗のオンライン展開を考えている方にもおすすめの内容です。
知識ゼロからのスタート!初心者のためのアフィリエイト入門 個人が小さく始める「ネットビジネス」の第一歩
副業解禁が進み、個人がビジネスに挑戦しやすい時代になりました。
とはいえ、「何をすればいいか分からない」「起業なんて無理」という声もまだ多く聞かれます。
そんな中、初期投資を抑えて始められる「アフィリエイト」というネットビジネスが注目を集めています。
この記事では、「知識ゼロ」からでも始められるアフィリエイトのビジネス的可能性や、仕組み・始め方をわかりやすく解説します。
社会人にこそオススメ!オンライン学習の効果的な使い方
近年、オンライン学習の市場が急速に拡大しています。YouTubeやアプリだけでなく、大学レベルの講義や専門スキルを学べるeラーニング、オンライン講座、資格取得コースなど、選択肢は多岐にわたります。 とくに「忙しい社会人」にとって、オンライン学習はスキルアップ・キャリアアップのための最強のツールとも言える存在です。 しかし、効果的に活用するには、学び方にもコツがあります。本記事では、社会人におすすめのオンライン学習の使い方と、その効果を最大限に引き出すためのポイントをご紹介します。
初心者でも簡単!オウンドメディアにも活用できるホームページ作成サービスおすすめ4選
「ホームページを作りたいけれど、何から始めればいいか分からない」「専門知識がないから外注に頼るしかないのでは?」そんな不安を抱える方は多いかもしれません。かつてホームページ制作はHTMLやCSSといった専門的な知識を必要とし、ドメイン取得やサーバー設定などの作業も複雑で、一般の方には高いハードルがありました。
しかし現在は、技術的な負担を感じることなく、誰でも簡単に短時間でホームページを作成できる時代になっています。そしてホームページを持つことは、単なる「情報の掲載」にとどまらず、信頼感の向上、顧客との接点の強化、ブランディングや集客の促進など、ビジネスにおいて多くのメリットをもたらします。特にSNSだけでは伝えきれない自社の強みや想いを、体系的かつ継続的に発信できる場として、ホームページは極めて重要な存在です。
また、多くのホームページ作成サービスではブログ機能やお知らせ機能も提供されており、オウンドメディアとしての活用も可能です。
クラウド会計ソフトとは?徹底解説!選び方と利用のメリット
起業したら、すぐに必要になるのが毎日、毎月の経費を記帳する会計ソフトです。しかし種類が多いのでどれを選べばいいかわからないという起業家さんは意外と多いです。また、高価なものは機能が充実し過ぎていて使いこなせるか不安になることもあります。 そうした中、近年「クラウド会計」といわれる会計ソフトが企業や個人事業主にとって欠かせないツールとなっています。特に、手間のかかる経理作業を効率化し、リアルタイムで財務状況を把握できるという点がクラウド会計の大きな魅力です。本記事では、クラウド会計ソフトの基本的な解説と、選び方、利用のメリットについて徹底的に解説します。
集客・宣伝を効果的に!SEO対策の具体的な方法、役立つサービスのご紹介
1)SEOはすべてのWebサイトの「見つけてもらう仕組み」
ホームページやECサイト、企業のブログなど、Webサイトを公開しただけではユーザーに届きません。本当に価値ある情報や商品を届けるには、検索エンジンで上位に表示されるための工夫、すなわちSEO(検索エンジン最適化)対策が必要です。SEOは広告とは違い、“無料で安定した集客”が見込める長期的な戦略として、多くの企業や個人事業者が取り組んでいます。本記事では、初心者でも実践しやすいSEO対策の基本と、作業を支えてくれるおすすめのサービスをご紹介します。
オンライン事業所年金情報サービスとは?メリットと導入方法をわかりやすく解説
今や、社会全体のデジタル化への対応、利便性向上を目的として、民間企業だけでなく、国や地方自治体などの公的機関の各種申請手続はオンライン上でできるような環境がほぼ整っています。身近なところでは「確定申告」も「国税電子申告(e-Tax)」が主流となり利用率も9割以上を達成したと言われています。また、地方税の申告から納税までの手続きがオンラインでできる「eLTAX」というシステムも急速に利用が広まっています。
これまで窓口に行って手続きしたり、紙を使ってやり取りしていたことも、オンライン環境が社会全体のスタンダードになりつつある現在、これらを上手に利用することが、会社経営が効率的になるのではないでしょうか。 ここでは、事業主の方の「社会保険料情報」の通知をオンライン上でいち早く受け取れる「オンライン事業所年金情報サービス」を紹介します。企業が従業員の年金に関する情報を一元的に管理し、必要な手続きをオンラインで行うためのプラットフォームです。
キャリアアップを目指す!今からでもできる社会人で楽しく英語を学ぶ
「英語ができれば、もっと仕事の幅が広がるのに」「昇進や転職に有利になると聞くけど、どこから始めればいい?」 そんな風に感じている社会人は少なくありません。英語力は、もはや一部の専門職だけのスキルではなく、多くの業界でキャリアアップに直結する武器になっています。 しかし、仕事や家庭で忙しい中、どのように学べばいいのか分からない、という声も多いのが実情です。 本記事では、社会人が無理なく、効果的に英語を学ぶための方法やポイントを紹介します。